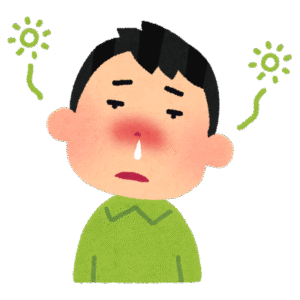7月の体調不良に注意!
7月は梅雨明けから本格的な夏になるため、気候の変化が大きく、様々な体調不良が起こりやすい時期です。主な原因としては以下のようなものが挙げられます。
1. 気温・湿度の変化による自律神経の乱れ
急激な気温上昇と高い湿度: 梅雨明けとともに気温と湿度が急上昇し、体がこの変化に適応しようとする際に大きな負担がかかります。体温調節を司る自律神経(交感神経と副交感神経)が、暑さに対抗するために汗をかき、血管を拡張させるなど、常に働き続けるためエネルギーを消耗し、疲労につながります。
高い湿度: 湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、体内に熱がこもりやすくなります。これにより、不快感や疲労感が増し、むくみやだるさ、頭痛などの症状が出ることがあります。
寒暖差: 屋外の暑さと、冷房の効いた屋内の温度差が大きいと、自律神経が頻繁に切り替えを強いられ、バランスを崩しやすくなります。これが、冷房病(クーラー病)の原因となり、頭痛、肩こり、腰痛、吐き気、むくみ、不眠、食欲不振など様々な症状を引き起こします。
低気圧: 梅雨時期は低気圧が続くことが多く、自律神経が乱れ、だるさや眠気を感じやすくなります。また、低気圧が続くとヒスタミンという炎症物質の分泌が多くなり、肩こりや偏頭痛が悪化することもあります。
2. 睡眠不足
気温や気圧の変化、暑さによる寝苦しさなどから、交感神経が優位になりやすく、リラックス状態になりづらいため、睡眠不足に陥りやすくなります。睡眠が浅いと疲れが取れず、イライラや集中力の低下につながります。
3. 食生活の乱れ・栄養不足
暑さで食欲が落ちたり、冷たいものばかり摂取したりすることで、栄養バランスが偏りがちになります。特に、タンパク質不足は免疫力の低下にもつながり、夏バテの悪循環に陥る可能性があります。
体内の余分な水分が引き金となり、消化器系に影響を及ぼし、だるさや食欲不振、消化不良、下痢や便秘を引き起こす「湿邪(しつじゃ)」という考え方もあります。
4. 脱水症状
湿度が高いと汗をかいても気づきにくく、知らず知らずのうちに体内の水分やミネラルが失われることがあります。特に、エアコンによる乾燥も脱水症状を進行させる可能性があります。脱水は熱中症のリスクを高めます。
5. 環境の変化(五月病の継続)
4月からの新しい環境への適応ストレスが5月病として現れ、7月まで継続して不調が顕在化することもあります。
6. 感染症の流行(特に子ども)
7月は夏風邪と呼ばれる感染症が流行しやすい時期です。主なものとして、以下のウイルス性疾患が挙げられます。
手足口病: 口腔粘膜、手足に水疱性の発疹が出る。幼児を中心に流行。
ヘルパンギーナ(夏かぜ): 発熱と口の中に水ぶくれの発疹を特徴とする急性ウイルス性咽頭炎。
咽頭結膜熱(プール熱): 発熱、咽頭痛、扁桃腺の腫れ、目やにが主な症状。アデノウイルスが原因。
これらの要因が複合的に作用し、7月は体調を崩しやすい時期となります。
対策のポイント
自律神経を整える: 適度な運動、規則正しい生活、十分な睡眠、ストレス解消を心がける。
室温・湿度管理: エアコンを上手に活用し、適切な室温(27~28℃が目安)と湿度を保つ。外気との温度差を大きくしすぎない。
水分・栄養補給: こまめな水分補給(ミネラルを含む飲料も有効)と、バランスの取れた食事を意識する。食欲がない時は、消化の良いものや香味野菜を活用する。
冷え対策: 冷房の効いた場所では羽織るものなどで体を冷やしすぎない。シャワーだけでなく湯船につかる習慣も大切。
感染症予防: 手洗いやうがいを徹底する。
体調が優れない場合は、無理をせず医療機関を受診することも重要です。
アプリコONLINEを利用すれば自宅にいながら医師に相談することができます。
いざというときの強い味方「アプリコONLINE」是非この機会にご登録してください。